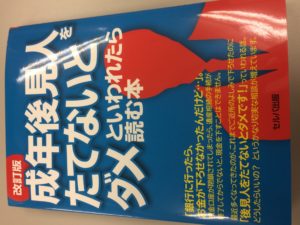行政書士の前田です。
昨今、どの業界も、人材不足で頭を抱えているそうです。
もちろん、私たちの業界も例外ではありません。
人の力は偉大です。替えのきく人など、一人もいません。
今の事務所では、採用活動にも携わらせてもらうことが
しばしばあります。共に働いた方々、面接でお会いした方々、
書類上でお会いした方々を含めるとたくさんの方々に出会ってきました。
その一人一人に多くのことを学ばせてもらいました。
この事務所を卒業(AKB風に言うと)した人からも、教えたことより
教えてもらったことの方が多かった気がします。
究極のところ、人材=人財、人こそ宝だと思います。
最近、勉強させていただいたと感じたある税理士事務所は、
たくさんのスタッフを抱えていますが、みなさん若い人ばかり。
対法人の仕事をする中で、若いことがマイナスに働くことがあるかと、
聞いてみたところ、
「たしかに若い人は多いが、経験年数は、10年近い人ばかり。
知識量が豊富であることを理解してもらえれば、年齢を気にされることは
ない」とのこと。
ここにも、大きなヒントが隠されています。
この事務所には10年近くその職場を辞めずに育つことのできる環境があるということです。
時間をかけて人を育てれば、強大な力になることを教えて頂いた気がします。
続いて別のお話。
月に一回、参加させていただいている勉強会にて紹介されたエピソードです。
私が尊敬してやまない松下幸之助氏のお話ですが、
彼は、社員の定着性をとても気にしており、朝一番に出勤して、
会社の入り口に立ち、「A君は出勤しているけど、B君がまだや」と
やきもきしては、社員全員の出勤を自分の目で確かめていたそうです。
所詮、自分の物差しで測れるものなんて、限りがあります。
きっとこの人は、こんな人間だなんて決めつけられるほど、
万能な物差しを持った人間などいません。
今、私は採用活動や教育をする立場にある以上、
人の可能性・成長をしっかりと見届けて人財を定着させることが
求められているのだと思います。
私も未熟者ですが、ともに成長できる方のご応募をお待ちしております。
誰にも評価されることのない魂の文章、書いてしまいました(笑)
前田